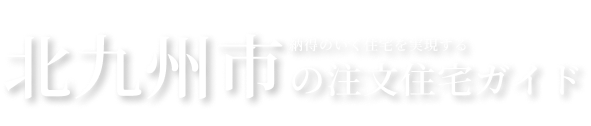北九州市で注文住宅を検討している皆さん、市街化調整区域って何だかご存知ですか?注文住宅を建てる際、この地域指定が住宅計画にどのように影響を与えるのでしょうか。
この記事では、市街化調整区域の基本から注文住宅建築のポイント、そして信頼できる工務店の選び方について詳しくご紹介します。
市街化調整区域とは? 詳しく解説
北九州市内には様々な市街化調整区域が存在します。市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
では、市街化調整区域とは具体的に何なのでしょうか?
都市計画区域の設定
都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。
そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。
市街化区域と市街化調整区域
都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。
具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化を抑える区域(市街化調整区域)を定めます。
この区分を定めることを「線引き」と言います。線引きは、多くの自治体において昭和40年代に行われました。
市街化調整区域の背景
戦後の高度成長期、都市部では人口の急増により住宅地の乱開発が問題となっていました。都市近郊では農業が盛んに行われており、乱開発が進むと貴重な農地が失われる危険がありました。
また、乱開発が進んだ場合、市街地が点在し、インフラ整備にかかる費用が増加してしまいます。このような状況を受けて、農村地帯を守り、効率的に市街地を開発するためには、開発の規制が必要だと考えられました。そのため、登場したのが「市街化調整区域」です。
こうした背景により、市街化調整区域は、政令指定都市や県庁所在地、中核市など、比較的大きな自治体で見られる傾向があります。
市街化調整区域の制限
市街化調整区域で開発を行うためには、土地の面積に関わらず開発許可を得る必要があります。開発とは、区画、形状、形質のいずれかを変更する行為を指します。
区画の変更
道路や水路を廃止したり、付け替えたり、新設したりすることで、その地域の利用形態が変わることを意味します。例えば、注文住宅を建設する際に道路の新設が必要な場合などがこれに該当します。
形状の変更
高さ1mを超える切り土や盛り土を行い、新たな土地を造り出すことです。例えば、擁壁を利用して斜面に平らな土地を作り、その場所に注文住宅を建てる場合などがこれに該当します。
形質の変更
農地や雑種地など、宅地以外の土地を宅地に変えること、または、土地の用途を特定工作物以外から特定工作物に変えることです。例えば、農地や山林などに注文住宅を建てる場合がこれに該当します。
開発許可は、開発を行う者が都道府県知事または指定都市の市長から許可を得る必要があります。申請を受けた知事や市長は、関連する法令に基づき、許可が適用される場合にのみ許可を出します。
市街化調整区域において注文住宅の建設が許可されるケース
市街化調整区域で注文住宅を建てるには、都道府県知事や市町から開発許可を得る必要があります。開発許可が下りるケースとして、以下の7つの条件が考えられます。
農林漁業者の住居
農林漁業者の住居は、都市計画法第29条第2号に基づき、開発許可が下りる場合があります。申請には業種ごとの条件を満たす必要があり、農業の場合は耕地面積10aや年間販売額15万円以上など、林業や漁業にもそれぞれの条件があります。農地を宅地に変更する場合、農地法の規制も関わるため、追加の手続きが必要です。
住宅兼店舗
自宅と店舗が一体となった住宅兼店舗は、都市計画法第34条第1号に基づき開発許可が下りる可能性があります。申請時には、「住居は補助機能であること」や「地域に貢献する店舗であること」を示さなければなりません。店舗の種類や基準は自治体により異なるため、事前に確認が必要です。
分家住宅
本家から分かれて建築される分家住宅は、都市計画法第34条第12号に基づき、開発許可が下りる場合があります。申請には「本家と同一世帯であったこと」や、「本家から相続または賃借した土地に建てること」などの条件を満たす必要があります。
既存住宅の建て替え
同規模・用途の住宅への建て替えは、既存宅地制度に基づき認められていましたが、2001年に廃止されました。しかし、自治体によっては依然として開発許可が下りる場合があります。申請時には、「宅地での建て替え」や「老朽化により建て替えが必要であること」を示さなければなりません。
親族のための住宅
6親等以内の血族、3親等以内の姻族のための住宅は、都市計画法第34条第14号に基づき開発許可が下りる可能性があります。申請には「市街化調整区域に20年以上居住する親族のため」や「線引き前から居住している親族のため」などの条件を満たす必要があります。自治体によって線引き時期が異なるため、詳細を確認することが重要です。
ディベロッパーが開発許可を得た土地を利用する
ディベロッパーが開発許可を得た土地は、一定の条件を満たせば開発許可が下りやすい傾向があります。例えば、ディベロッパーの分譲地に注文住宅を建てる場合などがこれに該当します。
立地条件を満たした土地を利用する
都市計画法第34条第11号に基づく立地条件を満たす土地なら、開発許可が下りる可能性があります。条件には、都道府県条例で指定を受けた地域、市街化区域と一体化した生活圏、環境保全への影響を与えないこと、建物間隔が50m以内で50戸以上が連続して建っていることなどがあります。自治体によって許可基準が異なるため、詳細な確認が必要です。
市街化調整区域に注文住宅を建てる方法・手順
市街化調整区域に注文住宅を建てるには、まずその土地が該当するか確認し、開発許可を申請する必要があります。多くの場合、行政書士事務所や建築・設計事務所が申請手続きを代行しますが、手順を理解しておくとスムーズに進められます。
市街化調整区域に該当するかを調べる
建築予定地が市街化調整区域に該当するかどうかは、自治体発行の都市計画図や土地利用計画図で確認できます。インターネットで自治体名と都市計画図、土地利用計画図を検索するか、直接窓口に赴いて相談する方法もあります。
自治体に相談する
開発許可の基準は一般的なものに加えて、自治体独自の条件が存在します。また、例外的に許可が下りるケースもあるため、土地を購入する前に自治体の窓口で必ず確認しておきましょう。
開発許可を申請する
開発許可の申請には、許可申請書や土地の登記事項証明書、位置図、配置図、平面図、公図の写し、自己用住宅を建築する理由書など、多くの書類が必要です。土地の性質に応じて異なるため、自治体に確認し指示に従って準備しましょう。農地転用が絡む場合や、立地条件が厳しい場合は、追加書類が求められることがあります。
自治体の審査・協議を受ける
提出した書類をもとに、自治体による審査・協議が行われます。追加条件が提示された場合、計画を変更する必要があります。農地や自然保護区に建設予定地がある場合、審査は厳しくなる傾向があります。
通知書を受け取る
審査・協議の結果として、開発の可否を知らせる通知書が発行されます。開発許可が下りた場合は、その許可を基に建築を進めます。許可が下りなかった場合は、計画の見直しが必要です。
建築許可を申請する
市街化調整区域に注文住宅を建てるには、開発許可に加えて建築許可を得る必要があります。開発許可が下りた後、その許可を基に建築許可を申請します。インフラや土地の状態に応じた計画をしっかりと立てることが求められます。
市街化調整区域で注文住宅を建てる利点と欠点
市街化調整区域内での注文住宅建設は、それぞれメリットとデメリットを考慮する必要があります。まずはメリットから見ていきましょう。
土地の価格が比較的安い
市街化調整区域は、一般的に市街化区域よりも土地の価格が安くなります。面積が広い土地を探している場合でも、比較的土地を見つけやすいでしょう。
固定資産税が低く抑えられる
市街化調整区域は、固定資産税が安くなります。建物の価値が低く評価されるため、税金負担が軽減されます。
静かな環境が手に入る
市街化調整区域内は、大規模商業施設などの建築が制限されているため、一般的に静かな環境が保たれます。都市の喧騒から離れて、のんびりとした生活を楽しむことができます。
一方で、市街化調整区域にはデメリットもあります。
インフラ整備が遅れる
市街化調整区域は、都市部に比べてインフラ整備が遅れることがあります。道路、公共交通機関、学校、医療施設などの利便性が低い場合があり、生活に不便を感じることがあるかもしれません。通勤や子育てを考慮する際には検討が必要です。
助成金の対象外になることもある
市街化調整区域内での住宅建設は、一部の助成金の対象外になることがあります。政府や自治体からの支援を期待する場合、対象エリアを確認する必要があります。予算面での影響を検討しましょう。
売却が難しい
市街化調整区域内に建てた住宅は、将来的に売却するのが難しくなる場合があります。土地利用制限が厳しいため、購入希望者が限られるためです。住宅の売却を考える場合、市場動向をよく調査し、リスクを考慮する必要があります。
市街化調整区域内での注文住宅建設には、価格の面での魅力や静かな環境がありますが、インフラの整備や将来の売却に関するリスクも存在します。計画を練り、将来を見据えて検討することが大切です。
住宅ローンが組みにくい
住宅ローンは、土地と建物の双方を担保として組まれます。市街化調整区域は売却が難しいため、担保としての評価が低く、審査対象外とする金融機関も少なくありません。
市街化調整区域に注文住宅を建てる際の注意点
市街化調整区域に注文住宅を建てるにあたっては、市街化調整区域ならではの注意が求められます。土地を購入してからの公開に繋がらないよう、注意すべき内容を確認しておきましょう。
規制を踏まえた設計が必要
市街化調整区域内で注文住宅を建てる際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、地域の指定によって建築高さや建ぺい率に制限があることがありますので、それに合わせたプランニングが必要です。また、外観や屋根のデザインにも規制がかかることがあるため、建築設計の段階から市街化調整区域の規制を踏まえたデザインを考えることが肝要です。
さらに、隣地との距離や日照の確保など、隣近所との調和も考慮しなければなりません。市街化調整区域内での建設は緻密な計画が必要となりますが、理想の注文住宅を実現するための鍵でもあります。
更地にすると再建築が難しくなる
市街化調整区域の土地を更地にすると、新たな建築許可が下りにくくなる場合があります。用途制限が厳しければ、再建築が不可となる可能性もあるでしょう。建て替えにあたっては、解体前の自治体への確認をおすすめします。
既に宅地でも建築許可が必要
建設予定地が既に宅地であり、区画・形状の変更がなければ、市街化調整区域であっても開発許可は必要ありません。ただし、開発許可の要否に関わらず、建築許可は得る必要があります。開発許可が要らないからと、建築許可の申請を忘れないようにしましょう。
住宅ローンに関するリスクマネジメントが必要
先ほど解説した通り、市街化調整区域は売却のしにくさから、住宅ローンが組みにくい傾向があります。申請者以外も再建築できるよう開発許可を得て売却しやすくする、住宅ローンが組めて初めて工事請負が有効になる「停止条件付工事請負契約」を結んでおくなど、適切なリスクマネジメントが求められます。
北九州市でおすすめの注文住宅会社を紹介
注文住宅の品質や性能、デザインは、会社によって大きく異なります。ここでは、北九州で注文住宅を検討されている方に向けて、おすすめの注文住宅会社を3社ご紹介します。
◇ACE
ACEは、断熱性能・気密性能・デザインを兼ね備えた注文住宅を提供する会社です。こだわりの断熱構造を採用し、これまでに800棟以上の住宅を建築してきました。断熱工法により、3つのスタイルから選ぶことができ、省エネや創エネ性能に優れたゼロエネルギー住宅や、60年の長期保証が付いた住宅なども実現可能です。
◇辰巳住宅
辰巳住宅は、素材・価格・デザインを重視した家づくりを目指す注文住宅会社で、福岡・北九州・筑豊エリアで活動しています。1983年の創業以来、建売住宅と注文住宅を合わせて3,500棟以上を手掛けてきました。注文住宅に加え、カスタムオーダー住宅や建売住宅の分譲も行っており、ZEH水準の省エネ住宅や省令準耐火構造、白アリや腐食が起こりにくい住宅など、さまざまなニーズに対応しています。
◇Inoue・Giken 井上技建
Inoue・Giken 井上技建は、遊び心を詰め込んだ唯一無二の注文住宅を提供する会社です。自社倉庫によるコストカットや、自社施工による高い技術力を活かし、多くの工程を自社で手掛けています。その結果、個性的で高品質な総無垢の住宅を実現しています。時間を要するものの、前例のないアイデアを取り入れた住宅や、職人の技術が詰まった住宅を提供しています。
市街化調整区域は都市計画法に基づく重要な制度で、都市の健全な成長を支える役割を果たしています。注文住宅を建てる際には、所在地がどの区域に該当するかを確認し、適切な許可を取得することが不可欠です。
また、市街化調整区域内での建設に際しては、地域の指定に従った計画やデザインが求められ、周辺環境との調和も大切です。
市街化調整区域の利点として、土地価格が比較的安く、固定資産税が低いこと、静かな環境が手に入ることが挙げられます。しかし、インフラ整備の遅れや助成金対象外、売却難のデメリットも存在します。
慎重な計画と適切な情報収集が、市街化調整区域内での注文住宅建設の成功につながります。個人では解決が難しいことも多いので、まずは地元の工務店に相談してみましょう。
「北九州市のおすすめ注文住宅会社3選」では、この他にも北九州で注文住宅を検討しているみなさんの土地探しに役立つ情報が満載です。ぜひ参考にしてみてください。