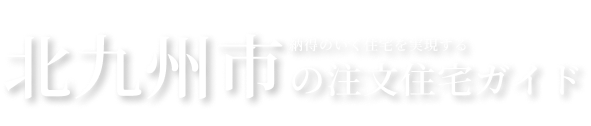2025年4月から、新築住宅には省エネ基準適合が義務化され、断熱性能等級4以上と一次エネルギー消費量等級4以上が求められます。高気密住宅はC値1.0㎠/㎡以下で、省エネと快適な住環境を提供します。
省エネ基準適合義務化とは?注文住宅への影響
2025年4月から、省エネ基準適合が義務化されます。これにより、建築物に求められる省エネ性能の基準が厳格化され、温室効果ガスの削減やエネルギー効率の向上が目指されます。すべての新築住宅・非住宅が対象となり、建築士が設計・監理を行います。
◇省エネ基準適合義務化とは
2025年4月から、省エネ基準適合が義務化されます。これは、カーボンニュートラルの達成を目指し、温室効果ガス46%削減を目指す改正建築物省エネ法に基づいています。
省エネ基準は、建築物が必要な省エネ性能を確保するための基準です。具体的には、断熱性能等級4以上と一次エネルギー消費量等級4以上が求められます。これにより、省エネ効果が向上し、環境負荷が軽減されます。
省エネ基準の具体的な内容は二つに分かれます。一つは、一次エネルギー消費量が基準値以下であること。もう一つは、外皮基準で断熱性能が基準を満たすことです。これにより、省エネ性能が向上し、温暖化対策に貢献します。
2025年4月から施行される改正建築物省エネ法によって、現在一部の建物のみが対象となる省エネ基準適合が、すべての新築建物に義務化されます。これにより、建物全体の省エネ性能が高まります。
◇義務化の背景
気候変動やエネルギー問題への対策として、世界的にカーボンニュートラルや脱炭素が進められています。日本でも温室効果ガス削減に向けた取り組みが強化されており、省エネ基準適合義務化はその一環です。
特に建物の断熱性能の向上や再生可能エネルギーの活用は、エネルギー効率の向上に直結します。これにより、温室効果ガスの削減とともに、持続可能なエネルギー管理が進むことが期待されています。
また、省エネ性能の向上は、環境への配慮にとどまらず、エネルギーコストの削減や生活の質の向上にも寄与します。これらの取り組みは、地球温暖化対策として非常に重要です。
◇省エネ基準適合の義務化後の影響
これまで省エネ基準の適合が求められたのは、主に大規模な建物に限られていました。しかし、2025年4月からはすべての新築住宅や非住宅に対して、省エネ基準の適合が義務付けられます。
これにより、建築士は新築の住宅や非住宅において、省エネ性能の計算を行い、その品質を保証する役割を担います。設計段階での省エネ対策がより重要となり、建築士の責任も大きくなります。
高気密な注文住宅の特徴
高気密住宅は、外気の影響を受けにくく、エネルギー効率が高い住宅です。気密性を示す「C値」が重要な指標で、1.0㎠/㎡以下を目指すことが一般的です。これにより、省エネや快適な住環境が実現されます。
◇高気密住宅とは
高気密住宅は、建物の隙間を最小限に抑え、優れた気密性を誇る住宅です。壁、床、天井、窓周りには断熱材や防湿シートを使用し、外気の影響を受けにくい構造を実現しています。これにより、室内の温度が安定し、エネルギー効率が向上します。高気密住宅では、外気との影響を極力排除するため、冬には暖かい空気が逃げず、夏には外部の熱の侵入を防ぎ、室内が常に快適な状態を保ちます。この構造により、冷暖房の効率が向上し、省エネルギーの観点でも非常に効果的な住宅形態と言えます。
高気密住宅の最大の特徴は、外気との影響を極力排除し、室内の温度を一定に保つことです。これにより、エネルギー消費を抑え、環境にも配慮した住まいとなります。また、気密性の高さにより、室内外の温度差を最小限に抑え、快適な室内環境を持続的に維持できるため、特に湿度が高い福岡などの地域で大きなメリットを享受できます。
◇気密性を示す指数であるC値とは
気密性とは、住宅の隙間を減らし、室内外の空気の侵入を抑える性能を指します。この性能が高ければ、高い省エネ効果を期待でき、冬の暖房や夏の冷房効率が良くなります。
気密性を表す「C値」は、建物全体の隙間面積(㎠)を延床面積(㎡)で割った数値です。C値が低ければ低いほど気密性が高く、省エネルギーに貢献します。理想的なC値を維持することが、高気密住宅の実現に不可欠です。
C値が低いほど、隙間が少ないことを意味し、温度管理がしやすくなります。これにより、冷暖房の効率が高まり、居住空間がより快適に保たれます。高気密住宅においては、C値の低さが省エネルギーと快適性を確保するための重要な要素です。
◇高気密住宅はC値1.0㎠/㎡以下が目安
C値は、日本における省エネ住宅の基準として重要な指標となっています。1999年の次世代省エネルギー基準では、5㎠/㎡以下が目安として採用されていましたが、2009年以降は、設計者や施工者が自主的に設定する基準となりました。
現在では、高気密住宅の目安として「C値1.0㎠/㎡以下」が広く普及しています。この数値は、省エネ性能の向上に貢献し、住環境の快適さを保つために重要な指標です。
多くの工務店や住宅メーカーは、C値の向上を目指して技術を進化させており、高気密住宅の普及が進んでいます。気密性の向上は、省エネと快適な住環境を実現するための不可欠な要素として認識されています。
断熱性能の高い住宅の特徴とUa値の基準
2025年から新築住宅には断熱性能等級4以上が義務化されます。高断熱住宅は、省エネと快適な室内環境を提供し、光熱費を削減します。Ua値などで断熱性が評価され、地域ごとの基準が設けられています。
◇高断熱住宅とは
2025年から、新築住宅において断熱性能等級4以上が義務化されます。これにより、断熱性能等級4が最低基準となります。高断熱住宅は、外壁、床下、天井裏に断熱材を使用し、外気温の影響を受けにくく、常に快適な室温が保たれます。この構造により、室内の温度が一定に保たれ、エアコンなどの空調機器を効率的に使用できます。
高断熱住宅は、温度設定を頻繁に調整する必要がなく、省エネ効果が得られます。また、光熱費を節約でき、室内全体や廊下との温度差も解消されます。さらに、高断熱に高気密を組み合わせることで、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を維持し、エネルギー使用量を抑えた快適な生活が実現します。
◇断熱性を示すUa値とは
Ua値(ユーエーチ)は、外皮平均熱貫流率を示す指標で、住宅の壁や屋根、窓など外気に接する部分から、室内の熱がどれだけ外へ逃げやすいかを示します。この数値は、外気に接する部分の熱量を外皮の総面積で割って算出され、Ua値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が優れた住宅になります。
日本では、2013年に国土交通省が「建築物省エネ法」を施行し、地域ごとにUa値の基準が設けられました。日本は8つの地域に分けられ、気候に応じた基準が設けられています。例えば、福岡県の北九州市は5~7地域に分類され、Ua値の基準は0.87以下となっています。
◇2025年に義務化される
2025年4月以降、すべての新築住宅に「断熱等性能等級4以上」が義務付けられます。断熱等性能等級は、住宅の断熱性能を示すランクで、数字が高いほど断熱性能が優れています。これは、政府が「2030年までに新築住宅の平均でZEH(ゼロエネルギーハウス)の実現」を目指しているためです。
現在の断熱等級は1~7まであり、等級1~3は旧基準に基づいています。施主が意識すべき基準は、等級4・5・6・7であり、これらの基準を満たす住宅は省エネ性能が高く、快適な住環境を提供します。
高断熱高気密のメリット
高断熱高気密の住宅は、快適で健康的な生活を提供するだけでなく、さまざまなメリットもあります。エネルギー効率が高く、環境にも優しい特徴を持つこのタイプの住宅は、生活の質を大きく向上させるため、多くの人々に選ばれています。具体的なメリットを見ていきましょう。
◇ 光熱費を節約できる
高気密高断熱の住宅は、外部の気温に影響されにくいという特性があります。夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができ、室内の温度が安定しやすいため、エアコンなどの空調機器の効率が大幅に向上します。これにより、温度設定を頻繁に変更する必要がなくなり、光熱費の節約が可能となります。さらに、部屋間の温度差を減らすことで、廊下や他の部屋でも快適に過ごせます。
◇ ヒートショックのリスクを軽減できる
高断熱高気密住宅は、室内の温度が均等に保たれやすいため、ヒートショックのリスクを減らすことができます。ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が急激に変動し、心身に大きな負担をかける状態を指します。特に冬場には浴室とリビングなどの温度差が大きくなり、ヒートショックのリスクが増しますが、このタイプの住宅では室内のどこでも一定の温度を保てるため、安全に生活することが可能です。
◇ 家が長持ちする
高断熱高気密住宅は、湿度の調整が容易であり、結露を抑えることができます。結露は、カビの発生や建物の劣化を引き起こす原因となりますが、高い断熱性と気密性を持つ住宅では、結露を防ぎ、家の長寿命化を助けます。また、十分な換気が行き届くため、室内の空気も常に清潔に保たれます。
◇ 洗濯物が乾きやすい
高断熱高気密住宅では、外気の湿度や温度が室内に影響を与えにくいため、梅雨や雨の日でも室内干しがしやすくなります。エアコンや空調機器を使用することで、室内の乾燥状態を保ち、洗濯物が短時間で乾きます。また、外気の影響を受けにくいため、花粉や黄砂が洗濯物に付着しにくく、衛生的な環境を維持できます。
◇ 防音効果がある
高気密高断熱住宅は、外部の騒音を遮断する性能が高いため、静かな生活環境を提供します。特に、赤ちゃんがいる家庭やペットと暮らしている家庭にとっては、室内の音が外部に漏れにくいため、近所に迷惑をかける心配がなくなります。逆に、外部の騒音も室内に届きにくいため、より快適な居住空間が確保されます。
後悔することもある?高気密・高断熱の家のデメリット
高気密・高断熱の家は、省エネで快適な生活を提供してくれる一方、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットについて理解しておくことで、建てた後に後悔しないようにすることができます。具体的なデメリットを見ていきましょう。
◇ 結露やカビが発生する場合がある
高気密・高断熱の家では、温度差が少ないため結露が発生しにくいと考えられがちですが、実際には結露やカビの問題が生じることがあります。結露は、暖かい空気が冷たい部分に触れることで発生しますが、施工時に壁と断熱材の間に隙間があると、そこに温度差が生じて結露が発生することがあります。さらに、換気が不十分な場合や施工不良があった場合、室内の湿気が外壁に伝わり、結露を引き起こすことがあります。これが原因でカビが発生しやすくなり、健康に悪影響を及ぼすこともあります。適切な換気や施工の品質を確保することが重要です。
◇ シックハウス症候群のリスクがある
高気密・高断熱の住宅は、外気と室内の空気の流れが少なくなるため、化学物質やカビ、菌類などが室内に蓄積しやすくなります。そのため、シックハウス症候群のリスクが高まる可能性があります。シックハウス症候群は、使用される建材や塗料、接着剤などから揮発する化学物質を吸い込むことによって引き起こされる病気です。症状としては、頭痛や吐き気、目の不快感、鼻水、気分が悪くなるなどが挙げられます。近年、建材に使用されるホルムアルデヒドなどの化学物質の使用は減少していますが、定期的な換気を行うことがシックハウス症候群の予防には欠かせません。
◇ エアコンなどの空調設備で室内が乾燥しやすい
高気密・高断熱の家では外気の影響を受けにくく、室内の湿気も外部に逃げにくいため、乾燥しやすい環境になります。特に冬場は、エアコンや暖房器具で室内が暖められることにより、空気が乾燥しやすくなります。これにより、肌や粘膜が乾燥し、健康に影響を与えることがあります。乾燥対策としては、加湿器の使用が考えられますが、加湿器を使いすぎると結露を引き起こす可能性があるため、適切な湿度管理が求められます。また、結露の発生を防ぐために、サッシや窓際にカーテンやフィルムを取り付けることが効果的です。
◇ 建築費用が高くなりやすい
高気密・高断熱の住宅を建てるには、通常の住宅よりも高性能な断熱材や気密材を使用する必要があり、それによって建築費用が高くなる傾向があります。また、施工にも手間がかかり、工事の工程が増えるため、費用がさらにかさむことがあります。高気密・高断熱の家は快適性や省エネ性能を重視した住宅ですが、その分、費用面での負担が大きくなる可能性があります。見積もりをしっかりと取ることが重要です。
高気密高断熱注文住宅の施工事例3選

高気密高断熱住宅では、動線や収納にこだわり、快適な生活空間を提供します。各住宅は広々とした空間を有効活用し、省エネ性能を高める工夫が施されています。
◇動線こだわった平屋の高気密高断熱住宅
この住宅は、UA値0.30(実測C値0.34)を実現した高気密高断熱の平屋です。広々とした平屋で、リラックスできる空間や水まわり、お仕事スペースが十分に確保されています。玄関からはキッチン、LDK、和室への3way動線が特徴で、特に和室は玄関から直接アクセスできるため、来客時にも便利です。また、家族全員が利用できるお篭り部屋としても活用できます。
寝室や個室はLDKから少し離れた場所に配置されており、落ち着いた空間で過ごすことができます。廊下からアクセスできるロフトもあり、収納スペースとして活用できるため、家全体がスッキリと整頓され、各ご家族が快適に暮らせる住まいが実現しています。
◇ロフトなどの空間にこだわった高気密高断熱住宅
UA値0.3(実測C値0.21)のこの住宅では、小上がりの和室や階段下のヌック、書斎、ロフトなど、多彩な居場所が豊富に取り入れられています。キッチンは壁付けデザインで、リビングスペースを広く確保。キッチンの奥には、お家型の可愛らしいヌックや階段下の収納も配置されています。
2階には、趣味室として使える書斎や、お子さまの個室があり、子ども部屋にはお気に入りの塗り壁カラーが施されています。広々としたロフトは主に収納スペースとして利用され、エアコン1台で2階全体の空調を効率的に調整する計画です。
◇クローゼットを各所に配置した高気密高断熱住宅
UA値0.55W/m²のこの住宅は、約48坪の土地に3台以上の駐車スペースを確保し、建築面積を有効活用しています。1階には居室、ファミリークローゼット、シューズクローゼットが配置され、さらに背面収納付きキッチンにより、ダイニングに散らかりがちな物をすっきり収納できます。
2階には各部屋に収納を完備し、主寝室にはウォークインクローゼットが設置されています。廊下にも収納スペースがあり、収納力たっぷりの住まいが実現しています。
北九州で注文住宅を建てるならおすすめ施工会社
こちらでは、北九州でおすすめの注文住宅会社を3社紹介します。
◇株式会社Ace

株式会社Aceは、北九州市を中心に展開する工務店で、低コストで健康住宅を提供しています。自由設計が可能で、3つのタイプから選ぶことができます。
全タイプがZEH基準を満たしているほか、上位プランにはHEAT20のグレードG1、G2に対応する高性能な住まいを提供しています。
このように、予算やライフスタイルに合わせた選択肢を提供することで、初めて注文住宅を依頼する方でも安心して利用できる工務店として人気があります。
| 会社名 | 株式会社Ace |
| 所在地 | 〒802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方5-9-32 |
| 電話番号 | 093-967-9114 |
| 公式ホームページ | https://www.kokura-ace.com/ |