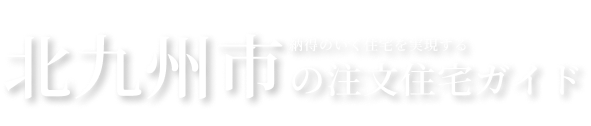ハイドアは床から天井までの高さがあり、開放感と明るさを演出します。選ぶ際は色とタイプに注意し、引き戸にすると開閉しやすいですが、設置場所に工夫が必要です。木下工務店は68年の経験を持ち、完全自由設計で顧客の要望に応え、50年保証と高い品質管理を提供しています。
注文住宅で人気上昇中のハイドアとは?
ハイドアは床から天井までの大型ドアで、部屋を広く明るく見せる効果があります。開放感を演出し、スタイリッシュな雰囲気を提供するため、注文住宅で人気が高まっています。
◇床から天井までの一体感を生み出す
ハイドアとは、床から天井までの高さがある大型のドアのことです。一般的な日本のドアは、天井高約2m40cmに対して高さが約2mで、上部に壁があるのが一般的です。ハイドアは、この上部の壁がなく、ドア全体が天井まで続いているのが特徴です。
◇開放感と明るさを手に入れる
ハイドアのメリットは、開放感を生み出し、部屋を明るく見せることができる点です。また、室内の雰囲気をスタイリッシュに演出する効果もあります。現在の注文住宅では、建物面積を抑える傾向があるため、ハイドアを採用することで、室内を広く明るく見せたいというニーズに応えることができます。さらに、コロナ禍の影響で家にこだわる人が増えており、ハイドアの高級感に魅力を感じる人も増加しています。
ハイドアを使う際に気を付けるべきポイント
ハイドア選びでは、色やタイプに注意が必要です。色は壁と合わせることで圧迫感を軽減し、引き戸にすると開閉が楽になります。設置場所としてリビングや玄関などが適しており、効果的に空間を演出できます。
◇色・タイプ
ハイドアを選ぶ際には、まず色とタイプを慎重に検討しましょう。ハイドアはその大きさから高級感や重厚感を演出できますが、場合によっては圧迫感を感じることがあります。
特に、ハイドア自体の存在感と壁の色とのコントラストが強いと、空間が狭く感じられることがあります。そこで、ハイドアの色は壁と同じ系統の色を選ぶか、明るめの色を選ぶことで、圧迫感を軽減することができます。
次に、タイプについてですが、開閉のしやすさを重視するなら引き戸をおすすめします。最近の注文住宅では、家事動線を考えた回遊動線が増えており、部屋の行き来がしやすい設計が求められています。頻繁に開け閉めすることが想定されるハイドアを引き戸にすることで、開閉のしやすさと仕切りの効果を向上させることができます。
ただし、引き戸では照明のスイッチやコンセントの取り付けが難しい部分があるため、注文時にその点を考慮しておく必要があります。
◇設置場所
ハイドアを選ぶ際には、設置場所を慎重に考えることが重要です。
ハイドアがよく使われる場所としては、リビングの間仕切りや玄関ホール、階段ホール、クローゼット、LDKに隣接するパントリーや洗面所などが挙げられます。これらの場所にハイドアを採用することで、室内のアクセントとして効果的に活用できます。
例えば、子ども部屋には通常のドアを使用し、玄関やリビングの入口にハイドアを設置するケースが一般的です。ハイドアは、ここぞという場面で取り入れると、空間をより印象的に演出できます。
木の魅力を最大限に引き出す木下工務店
木下工務店は北九州で68年の経験を持ち、完全自由設計で顧客の要望に応えます。厳しい基準で建築し、50年保証を提供。専門職人「キノシタマイスタークラブ」による直営施工で品質とコストの透明性を確保し、安全管理と技術向上にも力を入れています。
◇自由設計
北九州で木の魅力を最大限に引き出しながら、顧客の要望に柔軟に応えてくれるのが木下工務店です。創業68年の技術とノウハウを活かし、安心できる住まいを提供しています。
木下工務店の最大の特徴は「完全自由設計」です。好みや予算に合わせた設計を行い、その土地のルールをしっかりと考慮してプランニングします。
同社は「理想以上の唯一無二の住宅を実現すること」を使命としています。そのため、可能な限り自由度の高い設計で住宅を提供してくれます。
また、住宅の強度に関しても独自の厳しい基準を設けています。創業から60年以上の経験を基に、厳格な基準や法令をクリアした素材を使用し、建築を行っています。さらに、全ての住宅に「安心の50年保証」が適用されており、アフターケアも万全です。
◇家づくりのマイスター
木下工務店では、多くの家づくりの専門家が在籍しており、自由設計の住まいを手掛けています。同社には「キノシタマイスタークラブ」と呼ばれる職人たちがおり、技術だけでなく、顧客への配慮や細やかな注文にも対応できるように教育されています。これにより、職人たちが一邸一邸丁寧に建築を行う体制が整っています。
また、木下工務店は直営施工というシステムを採用しており、自社で職人を手配し管理することで、品質と予算の透明性を確保しています。このシステムにより、コストバランスの取れた住宅が提供されることも特徴です。
現場では「キノシタ マイスタークラブ」の職人たちが、安全管理を徹底し、定期的に技術や知識を向上させる研修を受けています。これにより、現場での安全性と品質の維持が図られています。
ハイドアですっきりデザインの施工事例

ある夫妻は、将来帰省する子どもたちのために広々とした実家を建てました。ハイドアや吹き抜けを取り入れ、開放感と機能性を実現。子ども部屋も柔軟に対応し、コストパフォーマンスとスタッフの対応が選定の決め手となりました。
◇将来の帰省を考えた家族のための住まい
ある夫妻は、「将来、家を出た子どもたちが帰りたいと思える実家を建てたい」という要望を持っていました。3人の子どもを育てるこの家族は、デザインや機能面でのこだわりを反映させるために、自由設計を選びました。
◇広々とした空間を実現するハイドア
ドア周辺に不要なラインが出ないようにするため、ハイドアを採用し、住まい全体を広々とした印象に仕上げています。また、2階のリビングには吹き抜けを設け、開放感を演出しています。さらに、ダイニングキッチンの収納を工夫し、リビングからバルコニーまで視界を遮らない間取りを実現しました。
子ども部屋は2つ設けられ、広さに違いをつけたうえで、広い部屋には成長に応じて仕切り壁を設ける設計がされています。夫妻は、家づくりを通じて自分と家族を見つめ直す機会が増えたと感じており、住み心地や機能性にも満足しています。
この家づくりにおいては、コストパフォーマンスやスタッフの対応が重要な選定要素となりました。
ハイドアは、床から天井までの高さを持つ大型のドアで、通常の日本のドアよりも高いのが特徴です。一般的なドアは、天井高約2m40cmに対して高さが約2mで上部に壁がありますが、ハイドアはそのまま天井まで続きます。これにより、開放感を生み出し、部屋を明るく見せる効果があります。
建物面積を抑えつつ、室内を広く感じさせるニーズに応え、高級感を演出するため人気が高まっています。
ハイドアを選ぶ際には、色とタイプを慎重に考える必要があります。大きなドアは高級感を出しますが、圧迫感を感じる場合もあります。そのため、ドアの色は壁と同じ系統か明るめの色を選ぶと圧迫感が軽減されます。
また、引き戸にすると開閉がしやすく、家事動線を考慮した設計が可能ですが、照明のスイッチやコンセントの取り付けに注意が必要です。
ハイドアを設置する場所としては、リビングの間仕切りや玄関ホール、階段ホール、クローゼット、LDKに隣接するパントリーや洗面所などが適しています。これにより、室内にアクセントを加え、印象的な空間を作ることができます。
子ども部屋には通常のドアを使い、玄関やリビングの入口にハイドアを設置することが一般的です。
木下工務店は、北九州を拠点に木の魅力を引き出しながら顧客の要望に応える注文住宅を提供しています。創業68年の経験と技術を活かし、完全自由設計を特徴としており、顧客の好みや予算に応じた設計が可能です。
また、土地のルールに基づいたプランニングを行い、理想的な住まいを実現します。
同社は、独自の厳しい基準を設けた住宅建築を行っており、60年以上の経験を基に法令をクリアした素材を使用しています。全ての住宅には安心の50年保証が付いており、アフターケアも万全です。
木下工務店には、多くの専門家が在籍しており、自由設計をサポートする職人たちが一邸一邸丁寧に建築を行っています。また、直営施工というシステムを採用し、自社で職人を手配・管理することで品質と予算の透明性を確保しています。